日本には存在してはいけない生物であり、日本の生態系を乱す恐れのある特定外来生物たち。
中でもアライグマは、非常に気性が荒く病原体を保有するため
もし住みつかれたら…。
子供やペットが襲われたら…。
そんな心配をする家庭も多いため、早急に何とか退治したいところでしょう。
しかし、アライグマを勝手に捕獲することは出来ず
資格や許可が必要になるんです!
そこで今回は【アライグマを捕獲するために必要な資格と許可】について解説していきたいと思います。
- アライグマの捕獲に関する法律
- アライグマの捕獲と処理について
- アライグマ被害を抑える対策法
アライグマを捕獲するための法的な問題
アライグマの捕獲は、日本の自然環境と生態系保護において重要な課題の一つ。
しかし、捕獲するためには法的な規制が伴います。
では、アライグマを捕獲するためにはどのような法的な問題が存在し、どのような資格や許可が必要なのでしょうか?
この章では、アライグマ捕獲に関わる法的な問題について解説します。
特定外来生物アライグマとは
アライグマは、日本の自然環境にとって異邦人のような存在。
かつてペットとして持ち込まれたアライグマが野生化し、今では日本のさまざまな場所で見かけるようになりました。
彼らは驚異的な繁殖力と適応力を持ち、生息数を増やし続けているんです。
北米から来たこの生き物が特定外来生物としての烙印を押された理由は明白。
- 日本固有の生態系に深刻な影響を及ぼすこと
- 農作物や住宅に被害をもたらすこと
- 人々の健康にもリスクをもたらすこと
このような背景から、アライグマの捕獲や駆除には環境省が定める厳しい規制が設けられており、これらの活動を行うには正しい手順を踏む必要があるんです。

アライグマ捕獲に必要な資格
アライグマを捕まえるためには、ただの意気込みだけでは足りません。
この仕事を適切に、そして人道的にこなすためには特別な資格が必要。
それが狩猟免許。
細かく分けると猟法によって必要な免許が異なり、以下の4種に分類されます。
- 第一種銃猟
- 第二種銃猟
- わな猟
- 網猟
この中で、アライグマを捕獲するためにはわな猟の資格を取る必要があります。(試験代5,200円・3年ごとに更新費2,900円)
この免許を手に入れるには【環境省】が提供する研修を受講し、その後、試験に合格しなければいけないんですよね。
法令や猟具の知識など専門知識が問われる事になり、独学では少し難易度が高いかもしれません…。
そんな場合、猟友会では予備講習会を定期的に開催していますので参加してみるのもいいでしょう。
試験に対する傾向と対策も分かりますから。
狩猟免許について詳しく知りたい方は環境省ホームページをご覧ください。
捕獲許可の申請プロセス
アライグマを捕獲するためには、ただ資格を持っているだけでは不十分。
なぜなら、野生動物は鳥獣保護法によって守られているからなんです。
鳥獣保護法とは?
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること
環境省HPより引用
勝手に行うと、外来生物法違反となり3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます!
捕獲に踏み切る前に、地方自治体への正式な許可申請が必須。
お住いの自治体によって細かな違いがありますが、一般的に必要な物は
- 狩猟免許の有無
- 害獣の種類
- 被害の場所・状況
- その地区の代表者
以上の項目を自治体に提出し、申請が通るまでは1~2週間ほどかかります。
申請が通れば【許可証】が発行され、駆除を行う際は許可証を携帯しておく事。
また、被害が深刻な自治体では狩猟免許が無くても許可が降りるケースもありますよ。
その場合は環境省が開催する捕獲従事者講習を受ける必要があります。(詳しくは環境省HPを参照してください)
この一連の工程は、アライグマを適切に管理し私たちの大切な生態系への影響を最小限に留めるために必要なことなんです。
アライグマを捕獲方法と処理
アライグマの捕獲とその後の処理は、地域の生態系保護と公衆衛生の観点から重要な課題です。
しかしこの作業を行うには、適切な方法と法律に基づく手続きの理解が必須。
この章では、アライグマを捕獲し適切に処理するための実践的なガイドラインについて解説します。
安全かつ効果的な捕獲方法
アライグマを捕獲する際、生け捕り罠の使用がおすすめ。
この方法なら、アライグマに無駄な傷を負わせることなく効率的に捕獲できます。
罠はアライグマがよく出没する場所である
- 食べ物を探しに来るエリア
- 隠れ家の入口付近
こういった場所に設置するのがベスト。
ただし罠を仕掛ける前にはその地域の法律をしっかりと確認し、必要な許可を得ることが大切です。
また、意図しない動物を捕まえてしまわないようにエサ選びや罠の設定には特に注意を払いましょう。
アライグマを惹きつけるけれども他の動物にはあまり魅力的でないような、マシュマロや果物をエサとして使うのが一つのコツです。
捕獲後の適切な処理
アライグマを捕獲した次のステップは、地域の法律やルールに沿って慎重に進めなければなりません。
まずは野生動物に詳しい専門家や地方自治体に連絡を取り、どう対処するか指導を求めるのが一般的な流れです。
感情的には
離れたエリアでアライグマを自然に帰したい!
と思うでしょう。
しかし残念ながら、ほとんどの地域でこの方法は許されず処理するしかないんですよね…。
そのため、どのように進めるべきか専門家のアドバイスが不可欠。
もし捕獲したアライグマの扱い方に自信がない場合は、野生動物の管理を専門とするプロの業者に依頼するのが、最も安全で確実な方法と言えるでしょう。
地域コミュニティとの連携
アライグマ問題への対応は、単独で行うよりも地域コミュニティ全体で取り組むことで大きな効果を期待できます。
しかし、どのようにして地域住民の協力を得て、統一されたアプローチを実施するのでしょうか?
この章では、地域全体でのアライグマ対策の実践方法について解説します。
地域住民への情報提供と啓発
アライグマの問題を根本から解決するには、ただ捕獲するだけでは不十分です。
地域の人々がアライグマについて正しく理解し、なぜこれらの生き物が特別な注意を要するのかを知ることが被害を抑える鍵。
このため、自治体や環境団体が主導して地域の人々に向けた教育プログラムや情報提供の取り組みが必要でしょう。
例えば
- ワークショップやセミナーを開催
- パンフレットの配布
- SNSでの情報発信
こういった方法で、アライグマの対策法に関する情報を広めていくことができます。
さらに学校での教育を通じて、子どもたちに自然との共生の大切さを教えることも、アライグマ問題に対する長期的な解決策に繋がるでしょう。
地域全体でのアライグマ対策
アライグマへの対応は、一人ひとりの取り組みを超え地域が手を取り合って進めることで真価を発揮します。
地域が団結してアライグマ捕獲の計画を練り、それを実行に移すことで問題の拡大を食い止めることが可能。
- 自治体
- 地域の人々
- 農家
- 環境保護団体
それぞれがアライグマを管理するための統一された計画を作り上げ、それを実行に移すことがカギとなります。
地域内で情報を共有するシステムを作り、アライグマの目撃情報や捕獲の成果をみんなで共有することで、より効果的に問題に立ち向かういましょう。
アライグマの捕獲に関するまとめ
今回は【アライグマを捕獲するために必要な資格と許可】について詳しく解説してきました。
アライグマが日本の生態系に与える影響は深刻であり、その管理には特定の知識と法的な手続きが必要です。
もう一度まとめると
- アライグマを捕獲するには資格と許可は必須
- 捕獲には罠が有効で処理する覚悟が必須
- 専門家のアドバイスは必須
- 対策には地域で連携することが必須
アライグマによる被害を防ぐためには、正しい知識と適切な行動が不可欠。
地域コミュニティと協力し、法的な要件を守りながらアライグマ対策を進めていくことをお勧めします。
最後まで読んでいただいて、感謝します。
私と一緒に、私たちの大切な自然環境を守りましょう。




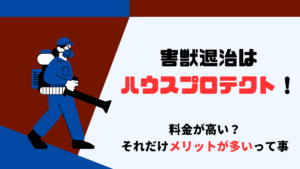
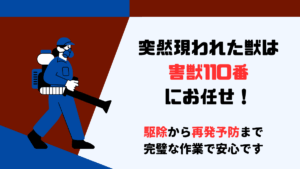
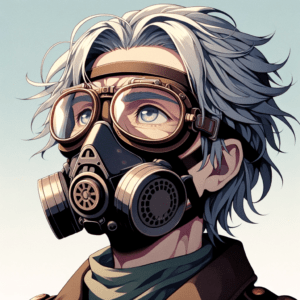
コメント